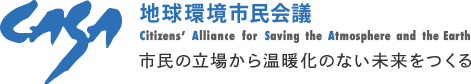気候変動対策・エネルギー政策について政党アンケート結果報告
2025.07.08. NPO法人地球環境市民会議(CASA)
参議院議員選挙が始まり20日には投開票が行われます。
2024年の世界平均気温は産業革命前よりも1.55℃上昇し、気候危機が現実になりつつあります。残されたカーボンバジェットを踏まえれば、早急な温暖化対策が不可欠ですが、第7次エネルギー基本計画やNDCはその危機感に見合ったものになっていません。温暖化を止めるには、国の政策転換が必要です。
私たちは、気候危機に真正面から向き合う議員を選ぶ一助とするため、各政党の温暖化対策に関するアンケートを実施しました。「第7次エネルギー基本計画、温暖化防止対策、原発・エネルギー問題」などについて回答をいただきました。ぜひ、投票の際の判断の参考にしていただければと思います(掲載順は提出いただいた順です)。
■回答をいただいた政党(回答の到着順)
NHK党、国民民主党、立憲民主党大阪府総支部連合会(立憲民主党)、れいわ新選組(れいわ)、公明党大阪府本部(公明党)、日本維新の会(維新の会)、社会民主党大阪府連合(社民党)、日本共産党大阪府委員会(共産党)
■7月7日現在回答をいただいていない党
自由民主党大阪府支部連合会(自民党)、日本保守党、みんなでつくる党、参政党、再生の道、改革党、チームみらい、日本誠真会
【質問1】
「第7次エネルギー基本計画」について
2月に「第7次エネルギー基本計画」が閣議決定されました。国会での議論はありませんでしたが、貴党の「第7次エネルギー基本計画」についての評価をご教示ください。(300字以内)
|
N H K党 |
第七次エネルギー基本計画は、再エネ導入の継続を掲げつつも、原子力や火力を一定程度活用する現実的な構成となっている点は評価できる。しかしながら、電源の安定供給確保やコスト抑制の観点からは、依然として再エネ偏重のリスクが残る。特に電力網への負荷や系統制約への対応が不十分である。NHK党は、脱炭素化を目的化するのではなく、国民の生活と産業活動を支える視点から、エネルギー政策全体の柔軟な見直しと説明責任の徹底を求める。 |
|
国民民主党 |
「第7次エネルギー基本計画」の策定される際に、エネルギー安全保障の観点からエネルギー自給率の向上を図りエネルギーを安全・安定・安価に確保することなどを盛り込んだ「第7次エネルギー基本計画に対する要請」を内閣総理大臣に申し入れました。安定供給の要である火力発電の高効率化、低炭素化、炭素回収・貯留(CCS)を促進するとともに、原子力や再生可能エネルギー等他国依存度の低い電源を積極的に活用することで、電源のベストミックスを実現するとともに、水素・アンモニア・合成燃料の国内製造基盤と利用環境の戦略的整備を進め、将来的なエネルギー自給率50%を念頭にエネルギー安全保障の確保を図ります。 |
|
立憲民主党 |
いわゆる「やっつけ仕事」感が否めない。加えて、確実性を過剰に意識するあまり、萎縮した形での内容となってしまった。計画というものは、やはり100%の達成が理想となるものの、一見、無理無謀とも思える目標値を掲げて設定することは、むしろ計画全体の推進力を押し上げたりもする。その意味でも、日本の姿勢を世界に示し、この分野で世界をリードするのだという気概に欠ける内容。第2、第3の産業革命ともいえるエネルギー分野を主導するのは日本であり、これからの日本は再生可能エネルギー関連事業で食べていくという意思をみせてもらいたかったと思っている。 |
|
れいわ |
第7 次エネ基には賛同できません。福島第一原発事故以降、第4 次から第6次までは、可能な限り原発依存度を低減する」との方針が維持されてきました。しかし、第7次では「最大限活用する」との文言となり、180度方針転換しています。また、2040年度のエネルギー見通し「リスクシナリオ」では、再生可能エネルギーの導入が進まず火力発電量が増加する可能性を示唆しました。結局、原子力発電と火力発電の延命を推し進める計画となっています。また、パブリックコメント4万件超の多くが原発活用に反対の意見でしたが、エネ基はほぼ原案どおり決定しました。そもそもエネ基策定に地域住民やNPO を参画させる仕組みが必要です。 |
|
公明党 |
第7次エネルギー計画の特徴は、電源構成の中で初めて再エネを最大電源に位置付けたことです。具体的には、再エネを「主力電源として最大限導入する」と明記し、40年度の構成割合を4~5割程度に引き上げ、23年度に電源の約7割を占めた火力発電は3~4割程度に減らすとしており、「再エネ最優先の原則」や2050年カーボン・ニュートラル実現への取り組みを評価し、エネルギーの安定供給と環境保全の両立を重視するのが公明党の立場です。特に、水素やアンモニアの利用拡大、浮体式洋上風力発電の早期実用化、次世代太陽電池の普及支援など、技術革新を通じたエネルギー転換を推進すべきとし、現実的で持続可能な政策への貢献を目指しています。 |
|
維新の会 |
ロシアによるウクライナ侵攻や中東情勢の緊迫化を受けたエネルギー安全保障の重要性の高まり、AI・データセンターの普及による電力需要増加への対応、2050年カーボン・ニュートラル実現を意識したものになっていて、基本的には妥当なものと捉えている。原子力発電政策については現実的なものと認識している。再生可能エネルギーについては記述が少し弱いと感じる。 |
|
社民党 |
第7次エネルギー基本計画について、原子力発電を推進する立場が明確に出ており、社民党のエネルギー政策と相容れません。特に老朽原発を延命させ、原発の新増設に踏み込む危険性を明確にしています。自然再生エネルギーを充実させ、蓄電能力を高めるなど、安定的なエネルギー供給を進め、あわせて省エネをさらに推進する必要があります。 |
|
共産党 |
福島第1原発事故は、いまだ収束の見通しさえ立たず、数万人が避難を強いられています。880トンもの燃料デブリを取り出せたのはわずか0.7グラムにすぎず、ALPS処理水の海洋放出処理の過程で発生する放射性物質を含む汚泥の保管容量はほぼ満杯となるなど、新たな問題が次々と持ち上がっているにもかかわらず、「基本計画」では、「原発依存度の低減」を投げ捨て、原発の「最大限活用」を明記し、原発の再稼働、新増設・建て替え、次世代革新炉の開発・設置をすすめるとしました。福島原発事故を「終わったもの」にして、原発回帰にかじを切ることは許されません。エネルギー基本計画は撤回し、国民的な議論をやり直すべきです。 |
【質問2】
温室効果ガス排出削減目標
政府は、2月に地球温暖化対策計画を閣議決定し、2035年の温室効果ガスの削減目標を国連に提出しました。削減目標は、2030年度の排出量を2013年度比で、46%削減は据え置き、2035年度は60%、2040年度は73%削減としています。政府はこの削減目標は1.5℃目標と整合しているとの見解ですが、COP28決定は2035年に2019年比60%の削減を要請しており、2013年比60%は2019年比では53%にしかなりません。貴党の2035年の削減目標についてのお考えをご教示ください。(200字以内)
|
N H K党 |
政府の2035年目標は、COP28決定と基準年が異なり、国際整合性に一定の課題がある。NHK党は、過度な削減目標がエネルギーコストや雇用に与える影響を懸念しており、経済合理性と国民負担の観点から慎重な検討を求める。削減目標は、現実的な技術進展と経済成長との両立を図る中で、段階的かつ柔軟に見直すべきである。 |
|
国民民主党 |
2050年カーボン・ニュートラル社会の実現や「パリ協定」の推進に向け、徹底した省エネルギーと、電源の低・脱炭素化や電化の推進、運輸部門における電動車の普及促進(インフラ整備を含む)、蓄電池やCO2フリーの水素・合成燃料(バイオジェット・e-fuel等)の開発・生産支援を行う等、革新的なイノベーションとその社会実装を通じた大幅なCO2削減をめざします。 |
|
立憲民主党 |
2035年の温室効果ガス削減目標については、国際社会が求める1.5度目標に整合する目標設定が必須であり、最低条件だと考えている。世界平均で2019年比60%の削減が求められているならば(IPCC)、これを満たすために、日本は2013年比66%以上の削減目標を設定するべき。「66%」ではなく「66%以上」として。 |
|
れいわ |
2030年までの目標として、石炭火力は全廃し、発電量に占める自然エネルギーの比率を50%まで高めることを目指すべきです |
|
公明党 |
公明党は、2035年までに温室効果ガス排出量を2013年度比で少なくとも66%削減するという高い目標を掲げるべきだと主張しています。これは、国際的な「1.5度目標」と整合する水準であり、将来世代への責任を果たすためにも必要だと考えます。 また、地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入促進や国民の行動変容を促す施策も重視しています。地域共生や生活の質の向上といった視点からも脱炭素社会の実現を目指しています。 |
|
維新の会 |
先ずは政府方針である2030年において温室効果ガスの2013年比で46%削減を達成することが最重要。そのためには、新たな投資を呼び込み、目標達成に不可欠な技術革新が必要である。これに伴い雇用創出も期待できる。この問題は経済政策への影響が大きく十分な配慮が必要。高い削減目標を掲げれば環境問題が解決するという単純な話とは考えていない。 |
|
社民党 |
社民党はもとより温室効果ガス排出量を2030年までに2013年度比で60%削減を目標としています。COP28決定に基づき、2035年までに2019年比で60%以上の削減を目標とするべきだと考えます。 |
|
共産党 |
日本共産党は、2013年度比で温室効果ガスの排出を75%から最大80%削減(2019年度比71~77%削減)するようめざします。エネルギー消費全体で6割減らし(電力消費量は3割削減)、再生可能エネルギーで電力を80%をまかなえば可能です。世界5位の温室効果ガス排出国であり先進国として、国連が求める「野心的な取り組み」に挑戦することで、2050年よりも前に「実質ゼロ」を達成する可能性を開きます。 |
【質問3】
石炭火力発電について
国際的には、「1.5℃目標達成のためには、排出削減対策が講じられていない石炭火力は先進国では2030年代にフェーズアウトすること」が合意され、石炭火力の廃止が進んでいます。日本政府には、石炭火力発電所の廃止の計画はなく、水素・アンモニア混焼、CCSの利用により、石炭火力の脱炭素化をはかるとしていますが、これらによる削減は最大でも20%程度に過ぎません。IPCCは「排出削減対策が講じられている」とは90%以上の削減がなされていることを意味するとしています。貴党の石炭火力発電についての見解を下記選択肢から選び、その理由をご教示ください。
① 石炭火力発電は、安定供給に貢献する電源として必要であり、石炭火力発電は脱炭素化をはかって存続すべきである。
② 石炭火力発電は、○○年までに廃止すべきである。
③ その他( )
(回答)
|
N |
国民 民主党 |
立憲 民主党 |
れいわ |
公明党 |
|
社民党 |
共産党 |
|
① 脱炭素化し存続 |
① 脱炭素化し存続 |
② 可能な限り早期に廃止 |
②
廃止 |
未選択 |
③ その他(環境負荷が低くエネルギー安全保障に有効な火力発電の技術開発促進) |
②
廃止 |
②
廃止 |
(理由)
|
N H K党 |
日本の高効率石炭火力技術(例:IGCC等)は世界最高水準であり、電力安定供給とCO₂削減の両立が可能である。NHK党は、これを国際的に活用すべきと考えており、脱炭素のために即時廃止するのは非現実的である。 |
|
国民民主党 |
現在、最終エネルギー消費の約5割を占める石油や天然ガスは国民生活・経済活動に不可欠なエネルギー源であり、安定供給の確保、価格変動への耐性強化、外交・戦略的価値等の観点から、燃料資源の探鉱、開発、生産といった上流権益を確保していきます。そのうえで、安定供給の要である火力発電の高効率化、低炭素化、炭素回収・貯留(CCS)を促進します。 |
|
立憲民主党 |
安定供給の第一となる石炭火力発電は、万一を考えれば、やはりある程度は残しておかなければならないと考えている。とはいえ、化石燃料に依存しない社会実現のためには、脱炭素未対応、未対応の石炭火力発電は、可能な限り早期の段階的廃止に向けた道筋を明確にしなければならない。したがって、(2)の回答には「可能な限り早期に」という言葉が入る。 |
|
れいわ |
石炭火力発電は、2030年までに廃止すべきです。すなわち、CO2排出量の多い石炭火力発電所の新設は禁止し、2030年までに石炭・石油火力発電所の運転を終了するべきです。 |
|
公明党 |
公明党は石炭火力発電の段階的縮小を進めるべきと考えます。特に、非効率な石炭火力の廃止を推進し、再生可能エネルギーの主力電源化を目指します。また、石炭火力発電の代替として、水素やアンモニアの活用、蓄電池の開発、送電網の強化などを通じて、安定的かつ脱炭素な電力供給体制の構築を重視しています。公明党は石炭火力発電を温室効果ガス削減の障壁と捉えつつ、現実的なエネルギー転換を支える政策を推進します。 |
|
維新の会 |
CCS(二酸化炭素の回収・貯留)、CCU(二酸化炭素の回収・有効利用)、CCUS(二酸化炭素の回収・貯留・有効利用)や石炭ガス火力発電など環境負荷が低くエネルギー安全保障に有効な火力発電の技術開発を推進すべきと考える。 |
|
社民党 |
2030年までに石炭火力発電をゼロにすべきです。横須賀市で石炭火力発電所が新たに稼働しています。新規建設の計画もあります。石炭火力発電所の効率性を上げるだけでは無理です。廃止を進めるべきです。 |
|
共産党 |
日本は、G7で唯一、石炭火力の廃止期限を示していないばかりか、今後も温存・延命しようとしています。各地の電力会社が再エネ発電への出力抑制を行っています。原発や石炭火力があるために、再エネ電力を「捨てる」など許されません。原発や石炭火力をやめることが気候危機に対する本気度の試金石です。すみやかに原発ゼロ、石炭火力からの計画的撤退をすすめ、2030年度はゼロとします。 |
【質問4】
原子力発電について
原子力発電は、GX脱炭素電源法が施行され、60年を超えて運転ができる制度が運用開始となりました。また、原発敷地内での建替が進められようとしています。この政策についての貴党の見解を、下記選択肢から選び、その理由をご教示ください。
① 安全が確認された原子力発電を今後も活用していくとともに、電源の安定的な確保のため、原子力発電の増設を進める。
② 原子力発電の再稼動等は認めるが、将来的には原子力発電に依存しないエネルギー政策をめざす。
③ 原子力発電は再稼働を認めず、40年を経過した原子力発電は廃止する。
④ 原子力発電の再稼働も認めず、即時廃止とする。
⑤ その他( )
(回答)
|
NHK党 |
国民 民主党 |
立憲 民主党 |
れいわ |
公明党 |
維新の会 |
社民党 |
共産党 |
|
① 増設 |
① 増設 |
② 将来廃止 |
④ 即時廃止 |
未選択 |
① 増設 |
④ 即時廃止 |
④ 即時廃止 |
(理由)
|
N H K党 |
NHK党は、原子力を安定供給の要として積極活用する立場である。再エネの不安定性を補完し、ベースロード電源として不可欠であると認識しており、新増設や建替えも選択肢に含めるべきである。 |
|
国民民主党 |
福島第一原発事故の教訓を踏まえ、安全確保を最優先としつつ、原子力発電を我が国の電力供給基盤における重要な選択肢と位置付け最大限活用します。次世代軽水炉や小型モジュール炉、高速炉、高温ガス炉、核融合炉、浮体式原子力発電等次世代革新炉の開発・建設(リプレース・新増設を含む)の推進、使用済燃料の処理・処分に関する革新的技術の研究開発、新たな発電・送電・蓄電技術や核融合技術の研究開発等を進めていきます。 |
|
立憲民主党 |
基本姿勢は原発の新設、増設は一切認めず。その上での(2)の選択となる。 |
|
れいわ |
地震国日本にとって、持続可能な経済の未来に、原発は不要である。直ちにこれを禁止する。実際のところ、2019年度実績で原発が供給したエネルギーは、電気の6.3%、一次エネルギー国内供給の2.9%に過ぎない。また、2014年には原発稼働ゼロでエネルギーをまかなった経験もある。原発を即時禁止しても、エネルギー供給には特段の問題はない。電力供給は主に天然ガス火力をつなぎとしながら、2050年までに自然エネルギー100%へと移行してゆく。 |
|
公明党 |
公明党は「原発に依存しない社会」の実現を基本方針としつつ、原子力規制委員会の厳格な安全審査に合格し、地元の理解を得た原発の再稼働は限定的に容認しています。新たな原発の建設や増設は認めておらず、例外的に「廃炉が決定した原子炉と同じ敷地内」で、地元の強い要望があり、かつ安全性が向上する次世代革新炉に限って検討対象としています。公明党は再エネ導入や省エネ推進を柱に、段階的な脱原発を目指しています。 |
|
維新の会 |
電力の安定供給に向け、原子力規制委員会の審査の効率をも重視した業務推進を進めつつ、新規制基準の許可を得ている原子力発電所の早期再稼動を進めるべきと考える。また、安全性の高い次世代原子炉の実用化に向けて研究開発に取り組むべきと考える。 |
|
社民党 |
GX脱炭素電源法では、脱炭素を口実に60年超老朽原発の稼働も可能としました。また、原発を稼働すれば放射性廃棄物(核のゴミ)も排出され、原発を廃止しても核のゴミは将来にわたって影響を及ぼします。環太平洋は火山も多く、プレートが集まっている日本は、世界の地震の約1割が起きており、地震大国で原発を稼働させる危険性は非常に高いと考えています。 |
|
共産党 |
世界有数の地震国・津波国日本で、「脱炭素」と称して原発を稼働させることは、東電福島第1原発事故から14年の現実や能登半島地震などを見ても無謀です。人間社会と地球環境に深刻な危険をもたらす原発推進は許されません。2011年の福島第1原発事故が発生して以後、北海道・東北・関東・中部・中国・沖縄の6圏では原発ゼロを経験してきており、原発をゼロにすることは可能であり、ただちに廃止すべきです。 |
【質問5】
再生可能エネルギーについて
日本の再生可能エネルギーの電源構成は、2023年度で25.7%で、世界的には遅れており、第7次エネルギー基本計画でも、2040年の再エネの電源構成比は40~50%に留まっています。20203年のCOP28決定では、2030年までに再エネの設備容量を3倍にすることが確認されています。2050年の脱炭素社会の実現にむけて、貴党の再生可能エネルギーについての政策をご教示ください。(200字以内)
|
N H K党 |
再エネは不安定かつ高コストな側面を持ち、電力の安定供給を妨げる要因ともなる。NHK党は、再エネのみに偏る政策には反対であり、現実的には原子力や高効率火力とのバランスを重視すべきである。コスト負担を抑えた形で再エネを技術革新によって段階的に導入する方針が妥当である。 |
|
国民民主党 |
S+3E を大前提に共生・自立・分散型のエネルギーネットワークを構築し、他国依存度の低い電源(再生可能エネルギーや小型モジュール炉(SMR)等)を中心としたマイクログリッドを含む自立・分散型エネルギー社会の構築をめざします。特に洋上風力、地熱の活用に注力するとともにジオエンジニアリングに取り組みます。2030 年代には電源構成比で再エネ比率が40%以上となるよう自治体等の関係者の合意を得つつ着実な取り組みを進めます。 |
|
立憲民主党 |
再生可能エネルギー最優先の原則を強く維持しながら、たとえば屋根置き太陽光や営農型太陽光発電、洋上風力、地熱、小水力、地中熱などの再生可能エネルギー導入を加速化させていくために、現行制度を検証する。併せて、障害となっている制度も見直していく。加えて、蓄電池や揚水発電などの蓄電設備の充実も同時に図っていく必要があると考えている。 |
|
れいわ |
2030年までにエネルギー供給の70%を、再生可能エネルギーでまかなうことを目指します。そして2050年までのできるだけ早い時期に再生可能エネルギー100%を達成します。脱原発・脱炭素までは既存の火力発電所を活用しつつ、新設を禁止し、2030年までに石炭・石油火力発電所の運転を終了します。暮らしの質を高めながらエネルギー利用効率を高め、2030年までにエネルギー消費量を40%削減し、2050年までに60%削減することを目指します。 |
|
公明党 |
自然エネ・再生エネの最大限の導入拡大のため、徹底した自然エネや再生エネの主力電源化に向けた取り組み等を更に強化します。具体的にはペロブスカイト太陽電池や浮体式洋上風力等の技術開発や社会実装の早期実現に向けた取り組み、サプライチェーン構築や人材育成、全国規模での系統整備、蓄電池の導入加速化等を進めます。また、再エネ促進区域等を充実・強化しながら、地域主導の再エネを促進します。 |
|
維新の会 |
再生エネルギーの導入促進や原子力発電所の再稼動によるエネルギー自給率の向上が重要と考える。2050年カーボン・ニュートラルの実現に向けて再生可能エネルギーの導入拡大や送電網整備、洋上風力や地熱発電の推進、核融合発電を含む次世代原子力発電、そして規制改革と投資促進を通じて、GXを強力に推進します。 |
|
社民党 |
脱炭素化実現のための火力発電所の廃止と原発廃止を進めながら、電源構成における再生可能エネルギーの割合を2030年までに50%、2050年まで100%を数値目標としています。 |
|
共産党 |
純国産エネルギーともいうべき再生可能エネルギーについて、環境省の調査でも、再生可能エネルギーの潜在量は、現在の電力使用量の7倍にもなると見積もられています。大手電力会社が原発や石炭火力を優先して再エネ電力の導入にブレーキをかける出力抑制を中止させ、再エネを最大限活用できるようにすべきです。そのために、東西日本レベルでの電力運営システムや、電力網などのインフラ整備を進めます。 |
【質問6】
エネルギー消費量の削減(省エネ)について
2050年の脱炭素社会の実現に向けては、エネルギー消費量の削減の取り組みも重要です。エネルギー消費量の削減(省エネ)についての貴党の政策をご教示ください。(200字以内)
|
N H K党 |
エネルギー消費削減は重要であるが、過度な節電強制や規制による経済活動の抑制は避けるべきである。NHK党は、民間の技術革新や市場メカニズムを通じた省エネを推進する立場であり、規制型政策ではなく、税制優遇や規制緩和などによる自発的取り組みを促すべきである。 |
|
国民民主党 |
デジタル化、カーボン・ニュートラルを長期的、計画的に促進するためグリーンイノベーション基金事業を見直し「DCN 基金」(仮称)を創設します。取得額以上の減価償却を認める「ハイパー償却税制」を導入するとともに、価格転嫁の促進を図ります。過度な負担により産業競争力を低下させることを避けつつ、あらゆる部門における省エネ化や電化の促進をはじめとする技術革新と社会実装によるイノベーションを推進します |
|
立憲民主党 |
AIやデータセンターの普及拡大が確実視され、今後さらなる電力需要の拡大が見込まれる。そのなかで考えなければならないのは、やはり省エネ。建物断熱や熱の有効利用、省エネ機器の導入など、現在ある技術の活用を促すとともに、画期的な省エネ技術が生まれるように、なにがしかのフォローアップは必要。この流れでの政策立案を、今後深めていかなければならないと考えている。 |
|
れいわ |
10年間で官民あわせて200兆円のグリーン投資を行い、再生可能エネルギーや省エネルギーのほか、エネルギー供給インフラや脱炭素化新技術などのグリーン産業で、毎年250万人規模の雇用を創出します。「燃料貧困」をなくすため、新規及び既存の戸建・集合住宅の断熱基準をさらに高めます。そして、快適で光熱費が低く抑えられるエネルギーゼロ(ZEH)公共住宅の建設をすすめます。また、省エネ設備導入のための支援を拡大します |
|
公明党 |
公明党はエネルギー消費量の削減に向けて、家庭や地域、産業部門での省エネ対策を重視しており、特に、住宅の断熱性能向上や「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)」の普及、既存住宅の省エネリフォーム支援の拡充を推進しています。また、「グリーンライフ・ポイント」制度の創設を提案し、環境配慮型商品の購入や省エネ行動を後押ししています。さらに、自治体への財政支援や再エネ導入の加速にも取り組んでいます。 |
|
維新の会 |
突発的なエネルギー価格高騰への対応能力強化やカーボン・ニュートラル実現の観点から、省エネの重要性がより一層高まっていると認識しています。事業者と家庭の両方向けの国と自治体を通じての省エネ設備への補助金と省エネ推進税制を充実します。 |
|
社民党 |
エネルギー消費量の削減は、重要な課題と認識しています。各家庭の電気消費量削減といっても地球沸騰化といわれ、夏場のエアコンの使用抑制は困難な状況にあります。しかし、省エネも進める必要があり、研究開発について、公費の投入が少ない現状を変える政策が必要です。軍事研究に多額の国費が投入されていますが、使い道を変える必要があります。 |
|
共産党 |
省エネを推進するために、断熱に優れた住宅・建物の普及、省エネに優れた機器への買い替え、EV車の普及や、公共交通などの利用による省エネ交通システムの整備を図ります。また、自治体と地域の専門家、実務者が協力し、省エネの診断を中立の立場での紹介・アドバイスを実施できるよう、支援組織の設立を進めます。さらに、地元企業が省エネ対策や再エネ導入で仕事を受注し、雇用が増えるよう協力や支援の体制を整備します。 |
【質問7】
参議院選挙での公約の優先順位
参議院議員選挙での選挙公約の中での、温暖化対策、脱炭素社会に向けての政策の位置付け(優先順位)について、貴党のお考えをご教示ください。(200字以内)
|
N H K党 |
NHK党は、温暖化対策を重要な課題と認識しつつも、政策の実施にあたっては国民生活への影響やエネルギーの安定供給、経済活動への負担を慎重に考慮すべきと考える。脱炭素化は目的ではなく手段であり、エネルギー政策の中で現実的・段階的に位置づけるべきである。経済・安全保障と両立する形での対応を優先する。 |
|
国民民主党 |
国民民主党の選挙公約の「政策4 本柱」の一つ、「2自分の国は自分で守る」の中に「原子力発電所の稼働・リプレース・新増設や核融合等で安価で安定的な電力確保とエネルギー自給率50%を実現、高効率火力発電によるカーボン・ニュートラルの推進」と記述しています。 |
|
立憲民主党 |
今次の参院選でのメインテーマは消費税、特に食料品関係の消費税の暫定的ゼロ化となるものの、ご質問にある温暖化対策、脱炭素社会への施策は以前からの大テーマ。プライオリティはなく、できるものから取りかかり、できるものから早期実現していくという姿勢で構えている。 |
|
れいわ |
れいわ新選組は今回の参議院選挙に際して、原発即時禁止とエネルギーの国産化で、全国津々浦々に産業と雇用を」進めるための施策を提案しています。地球温暖化対策と生物多様性保全は車の両輪であり、エネルギーの国産化は我が国の安全保障にも重要と考えています。 |
|
公明党 |
公明党は結党以来、公害や大気汚染などの環境問題を政治課題に取り上げ、地道に施策を進めてきました。それは環境を守ることが国民の健康・命を守り、未来を守ることにつながるからです。今後も“環境の党”として使命を果たすべく施策を強力に進めます。参議院選挙では、日本が直面する困難な課題を乗り越え、持続可能で活力あふれる日本を創るため、重点政策として地球温暖化対策・脱炭素社会に向けての政策を訴えてまいります。 |
|
維新の会 |
温暖化対策、脱炭素社会に向けての政策は極めて重要と認識しています。しかしながら、各々の政策の優先順位に関して順番を付すことは困難な側面があります。各々の政策には強い相互関連性があり、単純に区分できるものではなく、総合的判断が必要です。 |
|
社民党 |
社民党公約の「社民党7つの緊急提言」の1つを地震大国に原発はいらない! 原発ゼロ・自然エネルギー100%の社会へ、気候変動対策は待ったなしを掲げ、社民党では最優先の政策として位置づけています。これらは早急に進めていかなければなりません。 |
|
共産党 |
2021年9月に「気候危機を打開する2030戦略」を発表し、破局的な気候変動を回避するために取り組める時間は長くなく、10年足らずの間に、全世界のCO₂ 排出を半分近くまで削減できるかどうか、ここに人類の未来がかかっていると訴えました。それから4年を経過した今回の参議院選挙基本政策では、「気候危機打開へ、正面から取り組む政治に」を掲げ、このままでは「後戻り」できない破局的な事態に陥る死活的問題だと訴えています。 |
【アンケートの実施】
・アンケート用紙・フォームを配布(郵送もしくはメール)
・記入されたアンケート(データ)をメールにより回収
・実施者
NPO法人地球環境市民会議(CASA)(担当:竹村 久)
〒540-0026
大阪市中央区内本町2丁目1―19―470
電話:06-6310-6301(平日10:30~16:30)
メール:office@casa1988.or.jp <